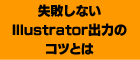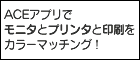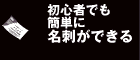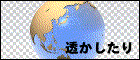|
|
 |
|
|
 |
|
|
|
|
●誰が色を決めるのか
少し前にある商品のパッケージを印刷した。そのパッケージにはカラー写真の素材イメージが使用してあったので、プロセスカラーの四色で印刷する必要があった。
一般にパッケージは特色(スポットカラー)で印刷するものが多く、多色刷りであってもプロセスカラーを使って印刷するものは少ない。カラーで印刷するよりも、二色や三色でカラーイメージの訴求力のある特色を使うほうが印象が強いのである。また板紙(ボール紙)は古紙の割合が高く、印刷機に通したときの伸縮が大きく、見当を合わせにくいこともあり、特色でトラッピング処理して印刷するのが普通だ。
プロセスカラーの印刷物なので、本来四色機で印刷すべきだったが、納期に間に合わせるためもあって、融通のきいた二色機でで印刷したところ、カラーのイメージ写真の色が変わってしまって、クレームがつく羽目になってしまった。
パッケージの印刷では二色機で四色を印刷することは珍しくはないが、色校正でやや赤みかがった色が印刷したときにベージュ色に転んでしまった。印刷したうえに菱レックスを貼ったこともあり、仕上がりのイメージは校正紙と比べて違いがさらに大きくなってしまったようだ。
結果論からいうと、たとえ納期に追われていても、色校正にも菱レックスを貼り、できれば四色機で印刷して印刷立会をすれば問題なく仕上がっただろう。がしかし、そこまでしなかったのはカラーといっても単なる素材のイメージに過ぎず、いままでも付合のある発注担当者がその部分にこだわると思えなかったからである。それよりも納期に間に合わせることが、優先されるべきだろうと判断したのである。
ところがパッケージがOEM商品であったため、発注担当者のさきに本当の発注者がいて、そこがクレームを付けてきたのである。色校正と違うではないかのと。
なぜクレームを付けてきたのかというと、色校正で写真取りをしてカタログを作っていたため、そのカタログの色と違うので駄目なのである、というのが本当のことらしい。だから正確には印刷された色に問題があるというより、ほかの印刷物と比べて整合性が取れないということが問題なのである。最初から印刷されたものとおなじ色で色校正が上がっていればなんら問題がなかったのである。
印刷物の色について考えるとき、一体誰がその色が正しいと判断するのかによって、印刷に対する品質への取り組みは変わってくる。インキの少しの違いでも受け入れない人もいれば、多少の違いは気にしない人もいる。色に対する許容範囲は人によって千差万別であり、私たちが印刷するときどのような過程で色にOKがでるのか、よく理解していないと、印刷したものを納品できなくなってしまう。
つまり印刷物は発注者にあわせて品質をカスタマイズしなければいけないものなのである。本当は高品質を要求する顧客には、それなりのコストを要求するべきだが、実際には印刷物の請求は顧客の懐具合にによって決まるので、高品質で手間のかかるものであっても、そのサービスに見合ったコストを請求できるわけではないのが実情だろう。 |
●色にこだわれば標準化はできない
商業印刷を主要業務としている会社は、誰と商売をしているのかというと、これは一般大衆ではなく、決まった相手とだけである。つまり消費者、コンシュマーとビジネスをするのではなく、特定のクライアントとビジネスをしているのである。
スーパーマーケットでは値札についてある金額をレジで支払えば、誰であっても「取引」ができる。しかし印刷物は数万円から数十万円、場合によっては数百万円以上になる非常に高い商品なので、誰とでも「取引」できるというものではない。こういう印刷物という高額の商品を買おうという人や企業は限られており、こうした高額の取引をするときにもっとも重要なファクターは、販売することではなく、販売した売掛金を確実に回収することなのである。
だから、取り引きするにあたっては、確実に売掛金を回収できる相手としか「取引」することはできない。とりわけ手形での受注になると三ヵ月や四ヵ月の売掛金が、取引残高となるので、もしクライアントか倒産すると毎月の売掛金の三倍から四倍の損失が生じることになる。スーパーマーケットでは棚の商品がもし万引きされたとしても取引全体から見れば、そのスーパーマーケットが致命的な損失を被ることはないが、手形での取引ではクライアントの倒産のあおりで、連鎖倒産することも珍しくない。連鎖倒産しなくても、簡単には取り返せない損失につながるとは間違いないのである。
こうした状況は印刷業界だけでなく、どこでもクライアント・ビジネスを展開しなければならない以上、宿命的であるといってよい。定期的な発注があり、しかも売掛金の回収が確実な企業との取引はどこも歓迎するところだから、こうしたクライアントとの取引は失うことはできない。
「お客様は神様」だが、クライアント・ビジネスでは「神様」を通り越して、さらに偉大な存在になる。しかもコンシュマー・ビジネスでは「お客様」は特定できない一般大衆だが、クライアント・ビジネスではっきりと顔の見える発注者であって、この発注者が「神様」になってしまう。
そうすると発注者の言うことは「仰せのとおり」とばかりに、平伏して聞くことになる。「値段が高い」といわれれば、値引きをすれば仕事になると思ってに当然のように値引きを行うし、「納期を短くしろ」しいわれれば、徹夜をしてまでも納期を合わせようとする。もちろんそうしないと仕事にはありつけないのであって、むしろ逆にいうと発注者の意向にさえ添えば仕事になるのであれば、発注者に気に入られれば安定して受注することが可能になるのである。
しかしこうして発注者にあわせていると、当然カラー印刷物の色も発注者によって品質基準が決められるので、クライアントによって、色の基準はマチマチになるわけだ。
デジタル化による商業印刷の市場の要求は印刷代を安くせよ、ということであった。デジタル化すればいままでの工程をショートカットすることができるので、コストは安くなるから、印刷代全体も安くなるだろうという考えがクライアントにあり、印刷代金は景気の動向と相俟って全般的に引き下げられた。印刷業界がデジタル化に邁進したのは、当然本音ではコストが下がるからであって、デジタル化することで本当にコストが下がり、以前より安い価格で受注しても利益が確保できる印刷会社が現れたのである。受注価格の引き下げに応じても、十分に利益を確保できる以上、価格を引き下げて受注を広げようとするのは当然の成り行きである。
デジタル化をさらに推し進めると、さらにコストを引き下げ販売価格も引き下げることが可能になる。ワークフローの組み方ひとつで、販売価格を引き下げても利益を生むことは可能だ。そして価格を引き下げれば、いままでそれなりの規模を持った企業以外にも市場をへ広げることが可能になる。しかしさらにコストを引き下げるためには、品質を一定にしていかなければならなくなる。そういう場合、クライアントの要望にあわせて、色をカスタマイズすることはできない。クライアントの要望に合わせて、色をカスタマイズするば生産性の高いワークフロー構築はありえないのである。
|
●品質を標準化すれば小口の市場が生まれる
印刷代を大幅に引き下げる唯一の方法は、印刷物を付け合わせるということしかない。受注にあわせてそのつど印刷機を回していれば、コストはそのつどかかることになるが、いくつもの受注をまとめて印刷すれば、各々の印刷代は飛躍して下がることになる。
こうした方法では、面積の小さな印刷物、名刺やハガキ、チラシ程度のものしか対象にならないが、しかし少ロットで小口の印刷物は以前から根強い需要があり、非常に低価格でカラーのハガキを付け合わせて印刷する印刷業者が存在していた。
デジタル化すると、こうした付け合わせは大変簡単になるので、これからも増えていくことになるだろう。
こうした小口の印刷物を付け合わせるためのポイントは、品質を印刷会社で決定できる相手でないと生産性の高いフローを作り上げることができないということである。紙の種類や印刷度数やインキの色については、あくまで印刷会社が決めたもので受注しなければならない。とくに色目については責任をもって請け負うことが必要になる。色校正を上げて色のチェックをユーザーが行うと、印刷や加工にかかる費用より、校正にかかる人件費の方が多くかかってしまう。そのため実質的にはコストを下げることはできないのである。だから低価格で小口の印刷物を付け合わせるには、色は印刷会社が決めなければならない。
小口の印刷物を付け合わせるのは、あくまで販売価格を引き下げ、より広くマーケットを求めることが目的だから、品質は二の次になる。最大限コストを下げたときに、どのような品質が考えられるのかということであって、印刷物としての仕上がりだけでなく、受注から納品・集金までのフローも含めてが品質なのである。つまり売り値を決めたときそれに見合った品質が適性品質というわけである。付け合わせる以外の印刷物でも、色校正をスキップさせることで、営業費などの人件費比率は明朗になるので、販売コストを引き下げることは難しくない。
百貨店などでバーゲンで売られるワゴン積みの商品は、確かにおなじような商品と比べて半値ぐらいであったりするが、シャツひとつとっても生地のランクがひとつ下だったり、縫製が貧弱だったりするのは当たり前だから、売り値に合わせて品質を考えるのは当然のことであろう。
こうした小口の印刷物を付き合わせるときの問題は、安い価格で発注するユーザーをどのように捕まえるのかということになる。しかも安定して一定価格で販売するためには、受注数が多く、しかもコンスタントでなければならない。
少なくともこういう色校正を行わない印刷物は、いままで印刷会社がクライアントとして受注していた企業などからの発注では決してない。だからいままでとは全く違う顧客を開拓しなければならない。こうしたユーザーはクライアントではなく、どちらかというとコンシュマー・ビジネス的な発想が必要となる。
たとえば年賀状ひとつをとっても、町中のDPIやコンビニエンスストアで販売して十分な市場があることをみると、たとえコンシュマーであっても、カラーの印刷物の潜在的な需要は十分予想できる。印刷物の価格が大きく下がれば、いままでオフセット印刷物を発注することは決してありえないことではない。 |
●マーケティングとは販売方法を決めること
マーケティングというのは、もともと舶来用語で非常に小難しい印象があるが、それほど難しくはない。一言でいうと、販売するモノやサービスがあって、それをどのようにそのモノやサービスを必要とする人や関心のある人に、知らせ、買ってもらうかということであって、そのためにどのように告知(広告)し、どのような販売方法と採用するのかということなのである。
告知する方法とは、マーケティングのどのメディアを採用するのかということであり、テレビやラジオなどのマス・メディアから、新聞の折り込みチラシなどまでさまざまな方法があり、もっとも効率のいいと思われる方法を選ぶことである。あるいはいくつかのマーケティング・メディアを組み合わせることになる。たいてい似たような商品とおなじ手法を選択することになるが、もちろん企業規模によって選択できるマーケティング・メディアは限られしまう。
告知方法が決まれば、あとは具体的な販売方法をどうするのかを決めればいいのであって、商品の特性に応じてある程度決まってしまう。たいていは販売方法は決まっているので、一般には告知方法も制限されてしまう。
はじめて販売するようなモノやサービスの場合は、どのようなマーケティング方法が最大の結果を導きだすのかをいくつかテストを行うことしかない。つまりテスト・マーケティングを行うことである。こればかりはどのように理論武装したところで、結果にかなうことはありえないから、やってみなければわからない。
印刷会社が小口の印刷物を集めるとすると、具体的にどのようなマーケティング手法がもっともいいのかは、テストを行うしかないのである。一般的にいって、ある程度絞り込まれたユーザー対象に告知することになるので、ダイレクトメールやテレマーケティングなどの手法が適当な思えるが、ひょっとすると新聞の折り込みチラシや雑誌広告がもっとも効率の高い方法かもしれない。
いずれにしても低価格の適性品質で、ビジネスチャンスを広げるには、マーケティングの手法を取り入れるしかない。いろいろ試してみて、もっとも適切で効率の高い手法をあみだした会社がこうしたマーケットに覇をとなえることができるのである。
一般消費財では品質はメーカーが独自の基準で決めるものだ。メーカーが一方的に決めることで、その品質では満足しない顧客は現れるかも知れないが、全ての顧客を満足させることではなく、品質の公約数と生産コストを天秤にかけて、品質を考えなければならない。それが「適性品質」である。
「適正品質」といったとき、もっとも重要なことはユーザーが魅力を感じる品質をそれに見合った価格で提供できるのかということであって、どのような品質にするのかを決めるのがもっとも難しい。最終的に適性品質を決めるためにはそれなりに試行錯誤が必要だが、クライアント・ビジネスでの収益が下がっている今、印刷会社でもコンシュマー・ビジネスでのマーケティングを視野にいれて営業活動を行わなければならない時期に来ているはずである。 |
●コンシュマー・ビジネスが新しいクライアント・ビジネスを生む
印刷会社としては基本的にはクライアント・ビジネスでなければならない。つまり発注量の多い企業なり団体から定期的な印刷物を受注していくことは、今後もおおきなウエイトを占めることは間違いない。
しかし既に大きくなってしまった企業と新たに取引をはじめることは大変な労力を必要とする。特別なコネクションがあって、なおかつ商品や価格などでオファーを行い、発注責任者や決済権者などに接待などを行うことで、はじめて口座が開ける。しかもなんども足を運び、取引が始まるまで長い時間を必要とする。運がよければ、それほどの労力を経ずして口座を設けることもあるが、それはただの僥倖であっていつもいつもそう簡単にはいかない。しかも口座が設けられたからといって一朝一夕に売上が確保されるわけではない。むしろそこから取引を広げることができず、それっきりになることも珍しくはない。 また、とりたてて理由もなく、簡単に発注をするようなところは、いままでの印刷会社とトラブルがあったり、支払に問題があると考えたほうがよいだろう。
もちろん大口のクライアントの中でもデジタルかを武器に魅力的な提案を行えば、耳を傾けてくれるところは少なくないだろう。そういった提案で他社のクライアントを攻めることは可能だが、ウエットな取引関係が強い日本では、アイデアに興味を示しても、いざ実行となると、今までの印刷会社に発注することが多く、企画して提案してもそれがすぐさま受注になるということはほとんどないのが実体である。
また取引が可能になったとして、現在発注している印刷物はすでに発注先が固定しているので、それらの仕事を奪い取ることには無理があるから、新しく発生する仕事を受注していくしかない。しかしそういう仕事をかき集めても発注量が大きくなるまでにかなりの時間がかかるので、受注額と営業費との収支バランスはなかなか釣り合わない。
そうなると、それなりに発注のボリュームがある企業を出来上がってから探してアタックをすることより、まだ大きくなる前に唾を付けておき、その企業が大きくなるとともに売上高を増やしていくほうが確実だろう。企業が小さいうちは、組織が完成しておらず、長年に亘って業者とのしがらみも少ないことが多く、取引を始めることは比較的容易い。
しかし今は小さいが今後大きく発展していくかどうかを、見極めることは誰にも出来ない。当初は町工場であったかつてのソニーやホンダが世界に羽ばたくことを予想した人がほとんどいなかったように、現在の企業規模をみてその企業の十年後を知ることはできない。
だからそういう大きく発展する企業と取引するためには、より多くのスモールビジネスと取り引きするしかない。たくさんの企業と取り引きするには、低価格の印刷物をマーケティングで展開することしかないだろう。たとえ千社のスモールビジネスのなかに三社しか、飛躍して発展する企業がなくても、そういう企業をクライアントに出来れば労せずして、クライアントを獲得することができる。もし千のうち三社飛躍して大きくなれば、クライアントとして取引できる企業はもっとも多く生まれるはずである。しかも小さな取引をしていくうえでは、リスクはほとんどないから、コンシュマー・ビジネスで間口を広げれば広げるほど、十年二十年先に大きなビジネスを見いだせる確率は高くなる。
デジタル化することで、コンシュマー向けの印刷物を「商品開発」することはそれほど難しくない。低価格の「商品」で新しいマーケットでビジネスを展開し、その中から、今後のクライアントを見つけていく、これこそが今後の印刷会社の取るべき正しいマーケティングの方法ではないのではないだろうか。コンシュマーが受け入れることができる「適性品質」を見つけだし、それに見合ったマーケティング手法を見いだせば、取引額は少なくても新しい販売先を見つけることは可能である。取引額は少なくても、より多くの取引先を見いだせば、新たな事業として十分成立するはずである。そしてそうしたマーケティングの結果が新しいクライアントの開拓にもつながっていくのである。 |
| このコンテンツは1997年2月10日〜12日に書かれたものです。 |
|
|