 |
| ▼ CONTENTS |
| ・はじめにお読み下さい |
| ・プロフィール |
| ・ブロードキャスト |
| ・Gordian Knot (ペーパーマガジン) |
| ・ウィークリーマガジン (メールマガジン) |
| ・デジタル
ビヘイビア (月刊PDFマガジン) |
| ・上高地仁の本 |
| ・ダウンロード |
| ・リンク集 |
| ・広告募集 |
| ・DTP-S倶楽部 |
 |
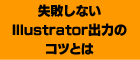 |
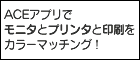 |
 |
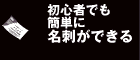 |
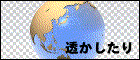 |
|
| << 戻る |
|
第二章 権利ビジネスの崩壊 フォントは目的か手段かそれが問題だ |
| もう少しデジタル上の権利について考えてみよう。権利関係ではたいへんあいまいなポジションにいる「フォント」の権利はどのように考えればよいのだろうか。 フォントはアプリケーションソフトに類するものか? というとそれは違う。正確にはフォントとして販売されているパッケージの中には、インストールのプロテクトがかけられているものがあり、そのプロテクト部分はプログラムされているものなので、そういう部分はアプリケーションソフトといってよい。プロテクトのプログラムは明きからに「道具」だからである。 さてフォントのデータそのものはどうだろうか。フォントといっても煎じ詰めればそれはデータの集合体にすぎない。ビットマップデータにしても、アウトラインデータにしても、基本はイメージ化するための素材であって、それだけではモニタに表示したり印刷したりはできない。表示印刷するための仕組みを通じて、はじめて形が現われる。 もちろんその形はイメージ化する方法を限定したうえで、使用できるもので、フォントを使用するときは、その最終イメージを使うときに権利について考えることになる。 文字はビットマップであれアウトラインであれ、字形というのは、その文字を作成した人のオリジナルといってもよい。だから「字形」を作り上げるという部分は「著作物」と呼んでもおかしくはない。 しかし日本の裁判の判例では、それを著作物としては認めていない。何故なら「字形」にオリジナリティがあっても、文字自体は古くから存在して、日本の文化の中で使われてきたものだから、文字のバリエーションに過ぎない「字形」に著作権を認めるわけにはいかないという。字形はいまあるものではなく、まったく一から独創して作られたものではなく、すこし工夫をした程度のものということなのだ。 だから権利はないというわけではないが、「著作権」には値しないという判断なのである。 しかしだからといって、文字のバリエーションには全く著作権が発生しないのかというと、そうではないだろう。たとえば書家の書いたものは、明きからに「著作物」といえるだろう。そこに書かれた文字というものは、その人でなければ表現できない文字の形しており、それは紛れもなく「思想又は感情を創作的に表現したもの」なのである。 書家の文字はたった一つしかない。たとえ同じ文字を書いていたとしても、別の紙に、別の時間に書けば、それは同じものではない。書家の書いたものが骨董品になったとき、書かれた時期によって評価が違うように、同じものを再生産するわけではないのだ。だからこそ、「書」には大きな価値があるのではないのだろうか。 そう考えたとき、著作権を有する「書」と著作権を認められない「フォント(あるいは書体)」には大きな隔たりがあることがわかるはずである。 フォントはあくまでも同じものを再生産するための道具であって、あくまでもモニタ上やプリンタでの出力で同じ字形を再生産するために提供されるものであって、クリエィティブなデザインを鑑賞するためのものではない。もちろんクリエィティビィティの違いは使用するフォントを選択するときの大きな要素とはなるだろうが、それでも、それは著作権で保護されるほどの「思想又は感情を創作的に表現したもの」とはいえないのではないか。 もし字形のオリジナリティに書家の書いたものと同じように価値があるというのであれば、フォントを額にいれてかざってみればよい。字形だけでも鑑賞に値するものであれば、その字形には大きな価値がある。 デザイナーが作成した字形に「著作権」を認め、それに対して使用料を払うべきだというのであれば、やはりフォントにせずに文字の形状だけで売れるかどうかやってみればよい。もしデザインされた字形に鑑賞する価値があれば、その文字は売れるだろう。 しかし一般にそういうことは広く行なわれているではないか。つまりロゴマークやタイトル文字を作成して販売するという行為は、実はデザインされた文字を売っているわけである。それは契約の仕方にもよるが、「著作権」を主張できるものであろう。 だが、フォントとして日本語の文字セットになったものは、創作された字形を売っているわけではなく、決められた文字セットをイメージを統一して作成されたものだから、著作物という要素はあるにしても、字形のデザインは文字を再現する道具としての一つの要素に過ぎない。 車のデザインだって工業デザインとして「著作権」を主張できるかもしれないが、エンジンを積まない外観だけの車を買う人はほとんどいない。車のデザインはあくまで同業他社が真似をしたときに主張するものであって、ユーザーには関係ない問題なのである。 つまり全体のバランスからいって、文字のデザインがフォントというツールに占める割合はそれほど大きいものではなく、創作された字形であったにしても、それは目的ではなくフォントを形作る手段なのである。 フォントはあくまでもコンピュータ上で文字を扱うための一つの手段であって、フォントデザインはそのバリエーションを提供するものだ。それを追及していくとしたら、フォントをどれだけ便利なものにしていくのかと言うことの方が重要になる。もちろん字形のオリジナリティも重要だが、それはフォントという道具が持ついくつかあるファクターの一つに過ぎない。 もう一度繰り返すが、フォントに一切の権利が存在しない、ということを言いたいわけではない。フォントにいま世間で考えられているような「著作権」を与えることはできないにしても、なにがしかの「権利」はあるはずである。ただ、いま法律では適切な方法がないと言うだけにすぎない。むしろフォントの権利関係があいまいなため、むしろフォントに対する世間の理解は狭まっているといえる。 ただフォントの権利の問題は、道具であるとということが忘れ去られ、権利問題に終止してしまうことが多いということだろう。権利を訴えれば、フォントの不法コピーが無くなるというのは、全くの幻想に過ぎない。 権利があるかどうかということではなく、権利があろうとなかろうと、道具である以上、どれだけの利便性を提供できるのかということの方が大事なのではないか。権利を主張するのではなく、むしろフォントをより多くのユーザーに使っていってもらうために、権利をどこまで放棄していくのか、また放棄するとしたらどのような方法で放棄していくのか、そしてそのうえでフォントビジネスをどのように構築していくのか、ということが大きなテーマだろう。 まったく同じ字形を別の名前を付けて、不法に販売するのは間違ったことだか、それ以外のことは全て権利は主張できなくなると考えたほうがよい。なぜならそれは権利以前の問題で、フォントを道具として使ってもらえなければ話にならないからなのである。 (1999/12/03up) |
|
「DTP-Sウィークリーマガジン 第41号(1999/11/27)」掲載
|
| << 戻る |

