 |
| ▼ CONTENTS |
| ・はじめにお読み下さい |
| ・プロフィール |
| ・ブロードキャスト |
| ・Gordian Knot (ペーパーマガジン) |
| ・ウィークリーマガジン (メールマガジン) |
| ・デジタル
ビヘイビア (月刊PDFマガジン) |
| ・上高地仁の本 |
| ・ダウンロード |
| ・リンク集 |
| ・広告募集 |
| ・DTP-S倶楽部 |
 |
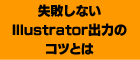 |
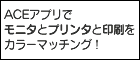 |
 |
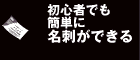 |
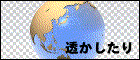 |
|
| << 戻る |
|
第一章 ビル・ゲイツ豹変す ドラマチック・アルバカーキ |
| 私がビル・ゲイツの名前を聞いたのは、はるかなる昔で、もう二十年も前のことだった。まだ学生で、しかもコンピュータを扱う理系ではなく、私の専攻は経営学だった。経営学部の選んだのは、入りやすかっのと経済学部より実用的かなと思っただけで、そういう意味では、わりといい加減な学生だった。ただ知り合いには、当時「マイコン」と呼ばれていたマイクロコンピュータで遊んでいる理系の学生がたくさんいたので、理系の話題にはついていけた。 そのときにビル・ゲイツはすでに有名人だった。そして私が耳にした話は「ビル・ゲイツがBASICを開発した」ということだった。もちろんそれは正しくない。ビル・ゲイツはBASIC言語を開発したのではなく、すでにあったBASIC言語を、はじめてのパソコンと言われるアルテア用に移植したのである。BASICを開発したのは、ダートマス大学のケイニーとカーツというふたり組みで、1963年に開発されたものだった。それ以前からあったものである。 しかしだからといって、彼の功績が劣るわけではない。いくらBASIC言語が優れていても、それが多くの人に使われないとしたら、価値は少なくなるに違いない。BASICを世間一般に広く膾炙させたのは、間違いなくビル・ゲイツなのである。 ビル・ゲイツの優れているところは、思いついたら最後までやり遂げることであり、それも即座に行動に移すことにある。そのために手段を選ばない彼の性格をして「大魔王」と呼ばれることもあるが、多分それは持って生まれた性格なのだろう。 エド・ロバーツはアルテアを開発すると同時に、当時の「ポピュラーエレクトニクス」という電子機器の専門誌に広告を載せた。そしてそれを見た当時のコンピュータマニアは、アルテアに殺到したのである。 アルテアはパーソナル・コンピュータと呼ばれていても、一部の好事家が使えるだけのものであり、パーソナルの所以は、仕事ではなく遊びや趣味に使えなくはないほどの価格であったため、「パーソナル」であったにすぎない。当時一番安いコンピュータはミニコンと呼ばれるもので、約四万ドル程度したが、アルテアは組立キットと同じくらい四百ドル以下で手に入れることができたからである。 多くの人が、アルテアでBASICを動かそうと思いついたらしい。というのはエド・ロバーツのところには、ひっきりなしにそういう電話がかかってくるのである。しかし実物を持ってきた物は誰もいなかった。 そこに実物を持って現れたのが、ポール・アレンだった。ビル・ゲイツとポール・アレンはアルテアの広告を見るなり、それでBASICを動かすことにビジネスチャンスを見い出し、その開発に没頭したのである。ピル・ゲイツはハーバードの学生だったが、このチャンスを逃すまじ、と学業を放り出してこれに専念した。誰かに先を越されたら、このプランはお蔵入りするしかないからである。 約3ヵ月の開発期間を経て、ビル・ゲイツとポール・アレンのBASICインタープリタは完成した。もちろんアルテアの実物となどない。広告に掲載された仕様だけを頼りに、BASICの移植を行なったわけである。正確に言うと、PDP-10というミニコンピュータにアルテアで使われてたインテル8080のチップをエミュレートして作ったらしい。いまの時代から考えると、なるほどと頷ける話だが、当時の発想ではアンビリーバブルな話だろう。とにもかくにも、一獲千金を夢見て、ふたりの青年は、アルテア用BASICインタープリタの開発を不眠不休で行なったのである。 エド・ロバーツがアルテアを販売するために設立した会社、MITS社はアルバカーキにあった。交渉は年長であるポール・アレンが担当した。もちろんボストンからアルバカーキへは飛行機代がかかるわけで、うまくいくかいかないかは神のみぞ知る以上、どちらか一人がいくしかなかったのである。 実機もないまま作られたビル・ゲイツとポール・アレンのBASICインタープリタは、最初はうまく動かなかったが、少し修正して動作するようになった。ビル・ゲイツはプログラマーとしての資質は飛抜けていないと言われるが、見もしないマシンを仮想してちゃんと動くプログラムを作るのだから、プログラマとしての資質は十分にあるはずである。 さて驚いたのは、エド・ロバーツの方だった。思いがけずちゃんと動くので、正式に契約することになった。 さあここでビル・ゲイツの面目躍如となる。 ポール・アレンから、契約ができそうだと電話で聞いたビル・ゲイツは、すかさずアレンに言った。「プログラムは売らずに、使用料を取れ」と。 ビル・ゲイツはもうこの時点で、ソフトウェアビジネスは権利を売らずに、権利の使用料でビジネスすべきことだと理解していたわけで、彼の商魂は、すでにこのときに形成され発揮されていたのである。 ソフトウェアの帝国を築いた人物は当然ソフトウェアのあるべき姿を理解していたのは、けっして偶然ではあるまい。しかし、ソフトウェアヒジネスの在り方は、その後大きく転回していくことになるのだ。 (1999/07/06up) |
|
「DTP-Sウィークリーマガジン 第12号(1999/01/14)」掲載
|
| << 戻る |

