|
|
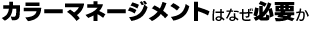
カラーマネージメントはなぜ必要なのでしょうか。カラーマネージメントツールを取り揃えて、適時モニタやプリンタのICCプロファイルを作成してカラーマネージメントすることでどのようなメリットがあるのでしょうか。「いままでカラーマネージメントしなくても、DTPはできたではないか」という声も聞こえてきそうです。
たしかに、モニタが正確なカラーを表示しなくてもDTPは成り立ちました。モニタといってもメーカーや機種が異なれば同じカラーでも表示される実際のカラーには違いがありましたし、同じ機種でも同じカラーを表示できるわけではありません。それでもDTPでカラー印刷は可能だったのです。
プリンタの出力紙を色校正代わりにすることも多くなりました。印刷機のカラースペースを無視して、プリンタからの出力紙にあわせて印刷することが一般的になりました。インクジェットプリンタではCMYKの印刷よりカラースペースが広く、インクジェットプリンタの出力は本来色校正には使うべきではありません。カラープリンタで再現されてもオフセットのカラー印刷では再現できない色は、印刷できないのです。レーザープリンタのカラースペースはオフセット印刷に近く、比較的オフセット印刷のカラーに合わせやすいのですが、レーザープリンタは出力する色が安定していないというデメリットがあります。
しかし、それでもカラープリンタからの出力にあわせて印刷することは珍しくなくなりました。
カラーマネージメントしなくても、DTPは可能です。ただしカラー品質は保証できません。色校正紙に合わせて印刷するだけですから、安定したカラー再現は難しいのです。
しかしこれから、DTPデータは印刷機のCMYKスペースを想定してワークフローを構築することが必要になるでしょう。いままで以上に納期を短縮するには、CMYKを指定して電子送稿するようになるからです。既存の技術を利用して納期が短縮できるのであれば、いずれ電子送稿は当然のものとなります。
電子送稿すれば、色校正紙に頼って印刷するのではなく、指定されたCMYKスペースにあわせて印刷することになります。つまり、カラーの基準が色校正紙ではなく、カラースペースになるのです。カラースペースが指定できれば、オフセット印刷でのカラーの再現は著しく正確になります。
DTPワークの中でそのCMYKスペースを確認するためには、カラーマネージメントするしかないのです。カラーマネージメントされたデータであば、Lab値をベースにしてカラーマッチングしてモニタの表示やカラープリンタからの出力で最終ターゲットのカラーを再現することができるのです。
いままでのカラーマネージメントはコストのかかるものでした。高価なデバイスがなければできませんでした。しかしいまでは、AdobeのDTPアプリケーションであれば、内部に組み込まれたAdobe
Color Engineでカラーマネージメントすることが可能です。
ただしAdobe Color Engineだけでは、カラーマネージメントはできません。モニタの表示にはモニタ用のICCプロファイルが必要で、カラープリンタからカラーマッチングのためには、プリンタ用のICCプロファイルが必要となります。
とくにモニタプロファイルは重要です。モニタの発色は固体差が大きく、経年変化もあります。Adobeガンマでガンマ値を調整しても、人間の目は調整したカラーに慣れてしまうため、ガンマ値のカーブでは正確なモニタ調整はできないのです。
モニタのカラー再現を正確にするためには、測色計を利用してモニタの管面のカラーや濃度を測定して正しいモニタプロファイルの作成が不可欠です。
| ●カラーマネージメントは万能ではないがカラーの再現性は高くなる
|
現在のDTPワークでモニタプロファイルが不要であっても、これから先、間違いなくキャリブレーションされたモニタプロファイルで、カラーマッチングされたカラーでモニタ表示しなければならなくなるでしょう。
それが「常識」になる前に、測色計を利用してモニタプロファイルやプリンタプロファイルを作成して、実際に利用してみることが必要です。カラーマネージメントがどのような仕組みで働いてるのかを知る必要があるのではないでしょうか。
もちろん、カラーマネージメントすれば、印刷でのカラーの再現が完璧というわけではありません。マネージメントするということは、誤差を認めるわけです。いままでの印刷では、印刷物の中でカラーを再現したい部分に優先順位があり、それに従って印刷していました。カラーマネージメントすると、優先順位という概念がなくなることも確かです。全体的にはより近いカラーで印刷されても、必要な部分の再現性が果たされなくなる可能性はあります。
しかし、カラーマネージメントすれば、印刷機でカラーをコントロールするにしても調整の幅が小さくなることも確かなのです。適当なCMYKを色校正にあわせて印刷するより、マネージメントされたカラースペースのなかの方がカラーのコントロールはやりやすくなります。カラーの再現を無理なく調整できるからです。
| ●コストダウンのためにはまずモニタプロファイルから |
初期のDTPはほとんど印刷の実務では役に立ちませんでしたが、それでも普及しました。DTPは実際にはよけいなコストを削減し、短納期を果たしたからです。
これから電子送稿が普及していくと、まちがいなく、印刷ターゲットのCMYKスペースを指定することが「常識」になります。そうなれば、モニタプロファイルでモニタをキャリブレーションすることも「常識」になるのです。
カラーマネージメントは必要不可欠のものとなります。そのためには、まず、モニタプロファイルの作成から始めましょう。モニタプロファイルを作成して、CMYKスペースを割り当てれば、モニタ表示で印刷したときのカラーを再現することができるのです。DTPのカラーマネージメントは、モニタプロファイルから始まるのです。
|
|